本記事のリンクには広告も含まれます
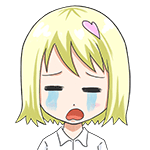
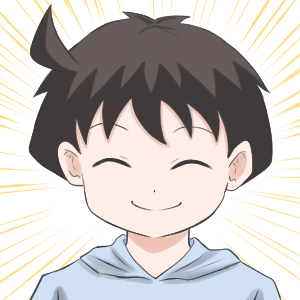
漫画の読み切り作品(短編)ってどうやって描いたらいいのか、難しいですよね。
わたしは漫画をかれこれ10年以上描いてます。読み切り作品も30は軽く超えています。
そんなわたしの経験や知識、テクニックをお伝えしようと思います。
本記事は、読み切り作品を描きたい人のために、そのストーリーのつくり方やコツを解説しています。
対象としているのはこんな人。
- マンガ賞に応募したい方
- 趣味でマンガを描いている方
- 短編マンガを描きたい方
これであなたも、漫画のストーリーがつくれるようになりますよ。
クリックできる目次
読み切り漫画のストーリー構成のコツは3つの要素を意識すること
マンガ雑誌の賞に応募する作品を想定して説明していきますね。
もちろん、趣味で描かれる方にも役に立つ内容です。
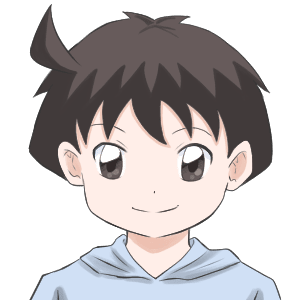
ストーリーを構成している要素を知ることで、面白さを作りだすことができます。
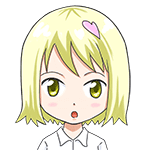
ストーリーを構成している主な要素は3つ。
- 作品のテーマ
- 登場するキャラクター
- ストーリー展開
読み切り漫画をうまく描けない方は、まずこの3つの要素を意識すればOKです。
では次から3つの要素を解説していきますね。
【要素1】読み切り漫画を描くためのテーマ
まずはストーリーをつくるためにテーマを決めましょう。
「テーマを決める」と聞くと、ちょっとメンドクサそうと思うかもしれません。
ですが、これは本当になんでもいいです。
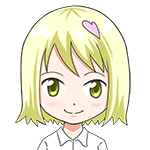
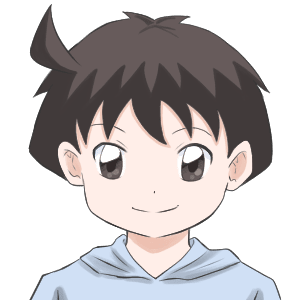
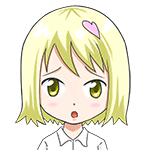
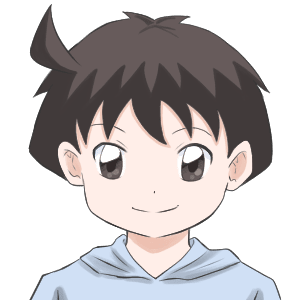
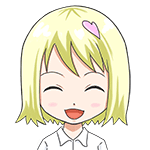
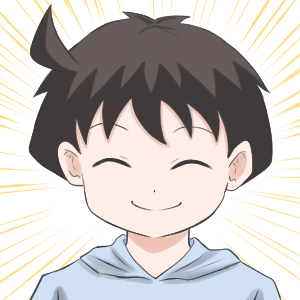
テーマを決めることは、描きたいモノを決めること。
それはアイディアベースでもいいですし、ふと思いついたモノでもいいんです。
そこから話が広がりそうなもの。具体的なエピソードが浮かびそうなものだったらそれがテーマとなります。
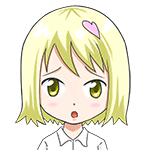
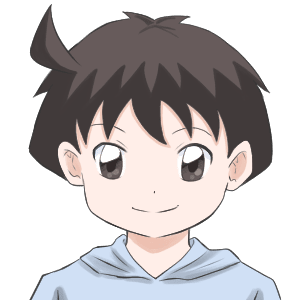
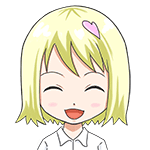

もうちょっとテーマをつめる必要がありますね。
ストーリーをつくるときに、感情だけを切り取って描きたくなる場合があると思います。
- 感動する話
- なんか楽しい雰囲気のやつ
- ほのぼのとしたの
- とにかく泣けるストーリー
しかし、これでストーリーをつくるのは困難です。
こういった感情だけのテーマだと、話の方向性や、具体的なエピソードまで掘り下げるのはかなり大変だからです。
もう少し、テーマとなる材料を見つけましょう。
たとえば、
- スポーツ系+感動する話
- 音楽系+楽しい雰囲気のやつ
- 動物系+ほのぼのとしたの
- 恋愛系+とにかく泣けるストーリー
これだと、ストーリーのイメージが浮かびやすくなりましたよね。
ここまで掘り下げられれば、ストーリーはつくりやすくなります。
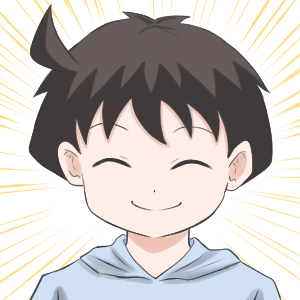
- スポーツ
- 音楽
- 恋愛
- アクション
- 動物モノ
- 食べ物系
- お笑い
考えればたくさん思いつきますよね。
もし「感動する」「楽しい」などの感情でストーリーが描きたくなったら、ジャンルと掛け合わせてみてください。
ちなみに、読み切り作品ではテーマは1つに絞りましょう。
音楽で夢を目指す。でも片思いの人とのラブストーリーも描く!
これはページ数が限られている読み切り作品では、すべて収まりきれません。
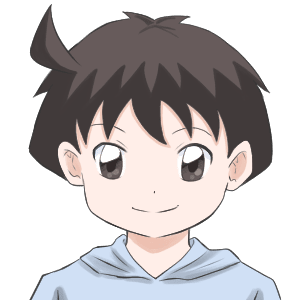
思いついたテーマは1つに絞り、ほかは次回作へ回しましょう。
それでもテーマに悩んだら、下記の記事を参考にしてくださいね。テーマの決め方を詳しく解説しています。
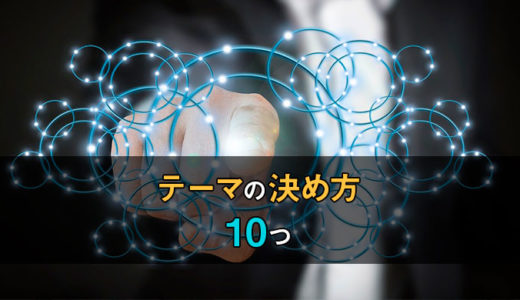 【漫画テーマの決め方】ストーリーが思いつかないときに試したい10の方法
【漫画テーマの決め方】ストーリーが思いつかないときに試したい10の方法
【要素2】読み切り漫画におけるキャラクター
読み切り作品などの短いストーリーでは、あまり多くのキャラクターはいりません。
- 主人公
- メンター
※主人公の手助けをしてくれる存在 - 敵役
この3キャラがいれば、十分読み切り作品を描くことはできます。
ではこの3キャラについて、作り方をそれぞれ説明していきますね。
主人公の作り方
主人公のつくりかたは、ズバリ!
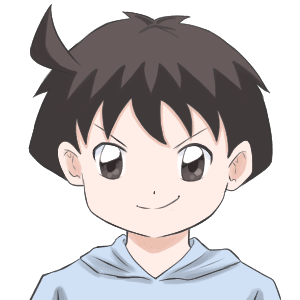
です。
例えば、「お坊さんに恋する話」をテーマとするならば、
- お坊さんについて詳しく知っている
- そしてその魅力に取りつかれている
そんなキャラクターを主人公とします。
そうすることで、『お坊さん』に恋する理由が生まれ、テーマを正確に読者に伝えることができるようになります。
もちろん説得力をもたすために、お坊さんに興味をもったエピソードも用意しましょう。
他の例でも、
上記のようにテーマに対して積極的な感情をもたすことが、テーマを伝えるキャラクター(主人公)となります。
主人公の設定する上で気をつけたい部分は、以下の記事を参考にしてくださいね。
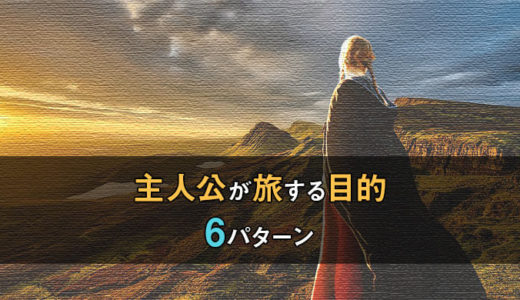 理由がないとダメ!主人公が旅をする目的6パターン
理由がないとダメ!主人公が旅をする目的6パターン
 【動機づけ】主人公の戦う理由の考え方とダメな例
【動機づけ】主人公の戦う理由の考え方とダメな例
メンターの作り方
メンターとは主人公の助けになってくれる存在のことです。
メンターの役割としては、
- 主人公の意思の強さを確認する
- 主人公を後押しする
- 主人公に危機を知らせる
- 展開が行き詰ったとき新たな情報をもってくる
などがあります。上記の役割を果たせるのであれば、主人公の友達や知り合い、両親、なんでもOKです。
『主人公を際立たせるために存在している』と、とらえましょう。
ではその役割ついてお話しますね。
主人公の意思の強さを確認する
メンターが主人公に意思の強さを確認するのは、読者を主人公に感情移入させるためです。
強い想いがある人ほど、その人を応援したくなりますよね。
主人公がお坊さんに恋したなら、
- お坊さんのどこがいいのか
- お坊さんに恋することの大変さ(デメリット)を説く
こういった会話をもちだし、主人公がどれだけ本気なのかを読者に伝えます。
妖怪退治のテーマなら、
- なぜ妖怪を退治するのか
- 妖怪の危険性
- 命の危機
などを伝え、主人公の覚悟の強さを読者に伝えます。
これがメンターの役割の1つ、 『 主人公の意思の強さを確認する』です。
主人公を後押しする
主人公を後押しするのは、ストーリーの展開をスムーズにするためです。
内容としては以下のような感じですね。
- お坊さんをホレさせる恋愛作戦を考えてあげる
- お坊さんの好みのタイプをリサーチして伝える
- 妖怪が出現する場所や時間を教える
その情報をもとに主人公を行動させると、ストーリーはスムーズに展開していきます。
これが『主人公の後押しをする』です。
しかし、ときには主人公の行動に注意喚起をうながすことも、ストーリーを面白くするうえでは大切です。
これが次項で説明する『主人公に危機を知らせる』です。
主人公に危機を知らせる
主人公に危機を知らせる内容は以下の通り。
- それをやると失敗するよ
- これはうまくいかないよ
- そこへ行くと危ないよ
- そんな武器では倒せないよ
上記のような内容を危険因子と呼びます。
うまくいかないことを案じさせて、読者の気を引きつける効果があります。
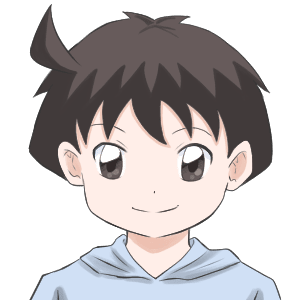
これが『主人公に危機を知らせる』です。
展開が行き詰ったとき新たな情報をもってくる
最後に『展開が行き詰ったとき新たな情報をもってくる』。
これはストーリーをつくっていて、行き詰ることがあると思います。
例えばこういうの。
- ここからどう展開させていこう
- こんな状況になったけど、どうやって解決させよう
- この後のストーリーがつくれない
そうなったときに、新しい情報をもってきて行き詰った展開を打破しましょう。
例としては以下のような感じです。
- お坊さんは○○がタイプらしい
- お坊さんが婚活パーティーに参加する
- その妖怪は○○が弱点
- 実は妖怪は和解を望んでいる
メンターの役割はたくさんありますが、必ずすべて使わないといけない!ってわけではありません。
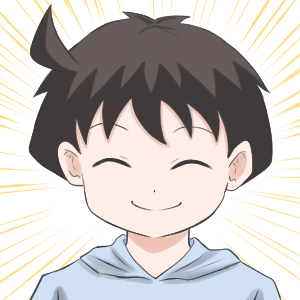
以上が、メンターのつくり方です。続いて敵役のつくり方。
敵役の作り方
敵役の作り方は簡単です。
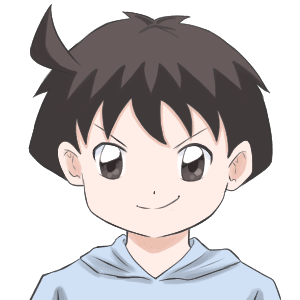
たったこれだけです。例えば主人公が
なら、主人公の敵役であるお坊さんは
と反対の価値観をもたせます。
妖怪退治がテーマなら、
なら、敵役である妖怪は
とします。
そうすることで主人公と敵役は対立・衝突し、ストーリーに面白さを出すことができます。
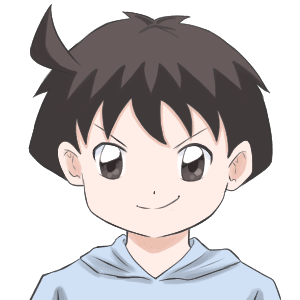
キャラクターの具体的なつくり方、キャラデザに関しては下記の記事をご覧ください。
 オリキャラの作り方は設定が大事!魅力的に作るコツを解説
オリキャラの作り方は設定が大事!魅力的に作るコツを解説
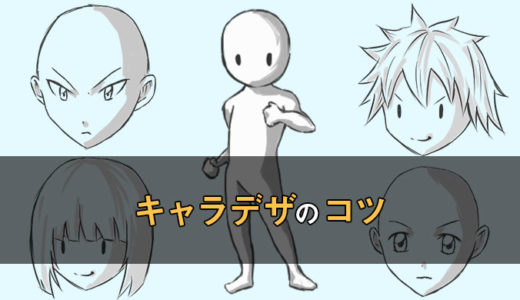 【キャラデザのコツ】キャラクターデザインの基本的な考え方はコレだ!
【キャラデザのコツ】キャラクターデザインの基本的な考え方はコレだ!
それでは3つの要素のうち残り1つ。ストーリーのつくり方を解説していきます。
【要素3】読み切り漫画のストーリー展開
簡単なストーリーのつくり方は、主人公の心の動きを追うことです。
「ストーリーをつくる」となると、話をどう展開させていけばいいのか
そればかりに気をとられがちですよね。
ですが大切なのは『主人公の心の動き』をエピソードにすることです。
先ほどから例にあげている「お坊さんに恋した主人」。このテーマに当てはめてみますね。
まずは主人公と敵役のキャラクターをおさらい。
- お坊さんに詳しい
- お坊さんの魅力にとりつかれている
- お坊さんに恋をした
- お坊さんに恋するやつはどうかしている
主人公と敵役であるお坊さんは、反対の価値観をもっています。
これを主人公の心の動きを追ったストーリーにすると…
かなりざっくりした流れですが、主人公の心の動きを意識すると、ストーリーはつくりやすくなります。
あとは、主人公の心の動きが飛躍しないように、心が変わる小さなエピソードを積み重ねていけばOKです。
大切なのは読者にその心の動きが理解できるか、共感できるか。
です。読者に
「いや、そうはならない」
「極端だな」
と、こう思われてしまうと読者は感情移入ができず、冷めてしまいます。
読者を共感させつつ、ストーリーを結末までもっていきましょう。
それでは実際にどうストーリーを展開していくのかを、なじみが深い「起承転結」にそって解説していきますね。
ストーリーの作り方「起」
ストーリーの「起」では、
- 主人公がだれか
- 主人公の目的はなにか
- 何についてのストーリーか
上記の内容を読者に伝えます。例でいえば、
- 主人公がお坊さんについて物知りなエピソード
- 主人公がお坊さんを好きになるエピソード
- 主人公がお坊さんを恋人にしようと意気込むエピソード
これを描くことで読者は「お坊さんとの恋を描いたストーリーなんだな」と理解してくれます。
まずはこういった設定を読者に伝えましょう。
ストーリーの作り方「承」
「承」では「起」で伝えた設定をもとに、ストーリーを展開していきます。
はじめの展開は、主人公の目的が順調に進んでいる様子を描きます。
お坊さんに接触し、積極的にアプローチする
これで一旦うまくいきかける展開を見せます。
しかし、お坊さんの
という価値観を読者に見せ、この対立構造を軸にストーリーを展開させていきます。
↓
対立構造によって目的を阻まれる
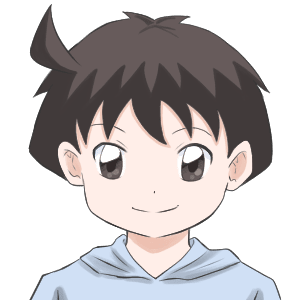
テーマや描くモノによっては、
↓
対立構造によって阻まれる
この1回の流れでも大丈夫です。
ストーリーの作り方「転」
「転」では今までと違った方法で、目的を達成するようにストーリーを展開させていきます。
例でいえば「承」でお坊さんへのアプローチ理由が、
でしたね。しかし「転」ではお坊さんというキャラクターの違う一面を見て、そこを好きになるエピソードを加えます。
そうすると、「お坊さんが好きだから」という理由でアプローチしていたのが
という理由に変わりますね。
「転」ではそういった「承」とは違う方向からストーリーを展開させます。
好きな理由も変わると、アプローチ方法も変わってきますよね。
理由とアプローチ方法が変われば、うまくいかなかった恋にも動きがでてきます。
「転」では「承」とはストーリー展開に変化を与えて、単調さをなくしていきましょう。
ストーリーの作り方「結」
「結」ではそのストーリーの結末がどうなったのかを見せます。
「転」ではストーリー展開に変化を与えましたよね。
それによって、主人公の目的がどう達成されたのかを描きます。
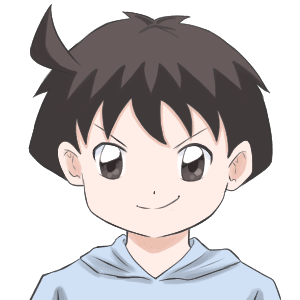
またお坊さんの例を見てみましょう。
「転」でお坊さんへのアプローチを
から
に変わりました。すると対立構造であった、
VS
お坊さんが好きなやつはどうかしてる
という構図は成立しなくなりますよね。
VS
お坊さんが好きなやつはどうかしてる
では対立のしようがありません。お坊さんの心の動きとしては、
けど…
と変化するはずです。
そうなれば、今まで効かなかったアプローチも効くようになりますよね。
アプローチが効くようになれば、主人公はお坊さんと付き合うという目的も達成できるようになります。
めでたし、めでたし。
このようにストーリーを展開させる流れを頭に入れておくと、読み切り作品は描けるようになりますよ。
読み切り漫画のページ配分
ストーリーの流れも大切ですが、ページ配分も大切。
よくありがちなのが「起」の部分が長く、早く本題にいかないパターンです。

「起」はフリの部分なので、できるだけコンパクトに見せて本題の「承」へ入ったほうがいいです。
ページ配分としてはこんな感じですね。
起:8 ~ 10 ページ
承:8 ~ 10ページ
転:3 ~ 5ページ
結:3 ~ 5ページ
起:8 ~ 10 ページ
承:20 ~ 22ページ
転:10 ~ 13ページ
結:3 ~ 5ページ
あくまで目安なので、多少前後しても大丈夫です。
ページ数が増えても、「起」と「結」、
つまり、はじまりと終わりは簡潔に。
「承」と「転」は必然的に長くなっていきます。
ぜひ参考にしてください。
本格的な読み切り漫画のストーリー構成のコツ!それは3つの要素で描くこと:まとめ
まだ読み切り漫画を描いたことがない、または描けない方は3つの要素を意識すると描きやすくなると思います。
その3つの要素とは
- 作品のテーマ
- 登場するキャラクター
- ストーリー展開
です。
また読切作品のつくり方は1つではありません。これは一例として受け止めてもらえればと思います。
ストーリーの作り方をいくつか具体的に記した本を出品していますので、さらに詳しく知りたい方はお手に取って頂ければと思います。
Amazon Unlimitedなら初月無料、または2ヶ月199円で読むことができます。
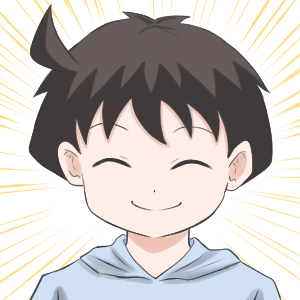
下記の記事ではストーリー制作に役立つ方法を解説していますので、あわせてご覧ください。
 初心者でもわかる!三幕構成でのストーリーの作り方を徹底解説!
初心者でもわかる!三幕構成でのストーリーの作り方を徹底解説!
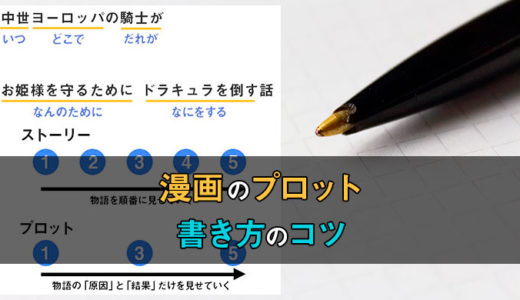 【解説!】漫画プロットの書き方のコツはたった3ステップだけ!
【解説!】漫画プロットの書き方のコツはたった3ステップだけ!
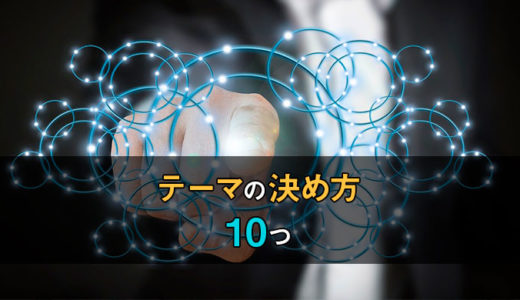 【漫画テーマの決め方】ストーリーが思いつかないときに試したい10の方法
【漫画テーマの決め方】ストーリーが思いつかないときに試したい10の方法
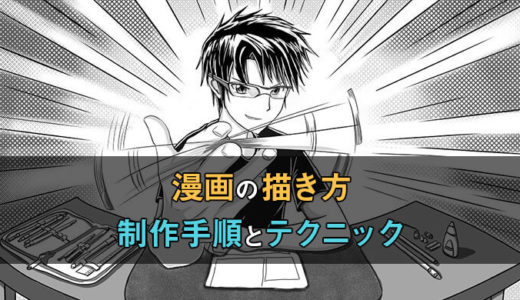 【漫画の描き方】制作手順と初心者でも身につくテクニックを伝授
【漫画の描き方】制作手順と初心者でも身につくテクニックを伝授

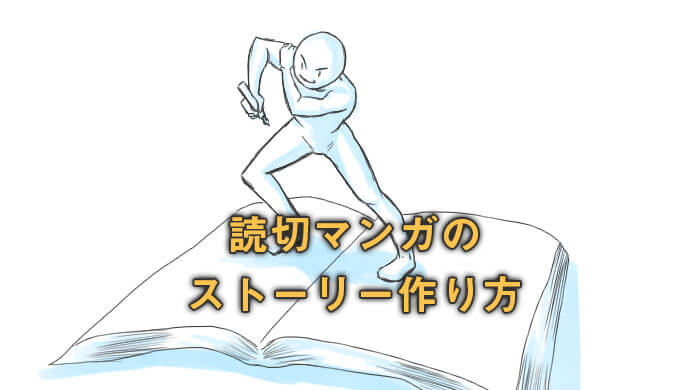
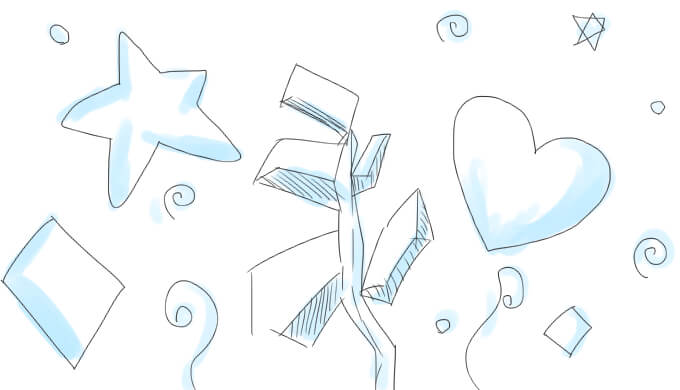
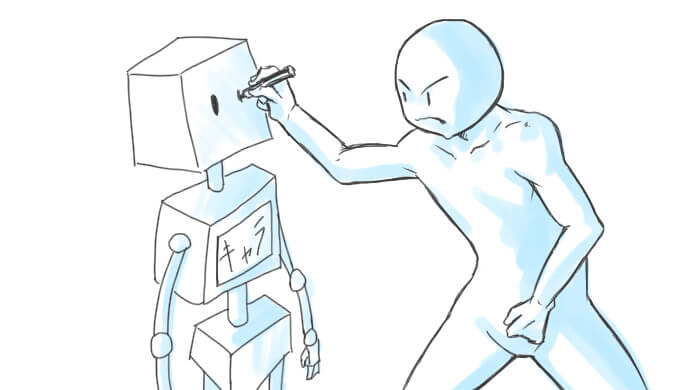
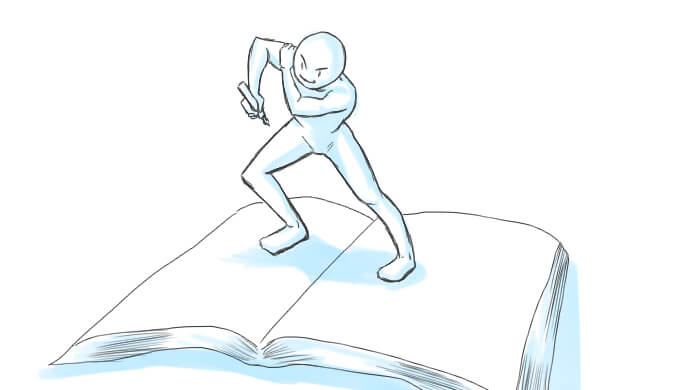
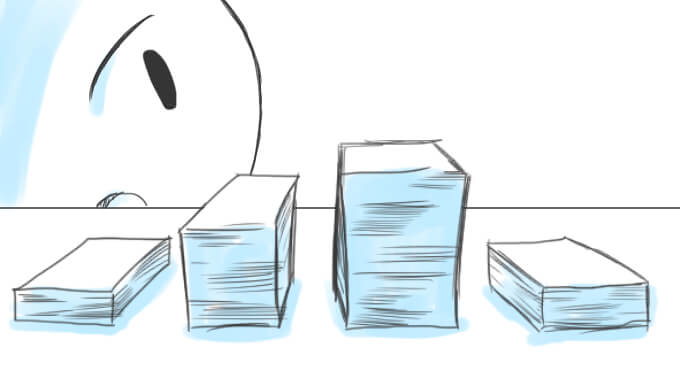


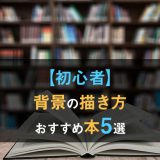

ありがとうございます。参考になりました。
ここのところ不安になることが多くて自分には才能がないのだと
絶望していましたが、あなたの記事で少し希望が見えました。
はじめまして。和々寺らおんと申します。
上手くいかないと辛いと思います。私も何回も絶望していました。
この記事が少しでもお役に立てたのなら嬉しい限りです。
応援しています。